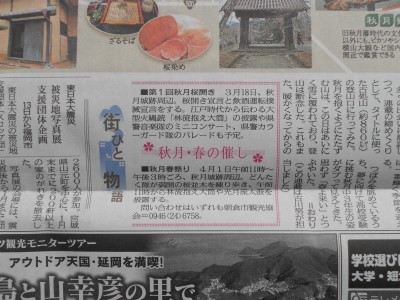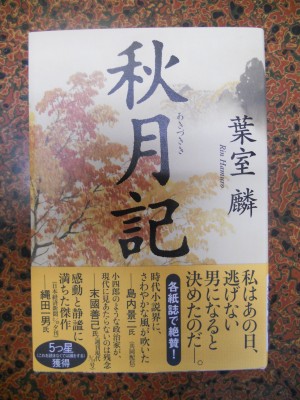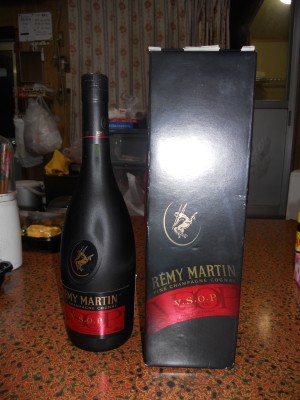秋月の歴史、伝統、文化、秋月人を紹介して頂きました。
タイトル通り、今、秋月は、静寂に包まれています。
古処さんは、いまだに雪化粧をし、盆地らしく底冷えをする寒さ、身を切るような水の冷たさ
しかし、これも秋月の風物詩です!
この底冷えのする寒さ、身を切るような水の冷たさが、なければ、良質の本葛を作ることが出来ません!
静寂と寒さの中、本葛作りは、熱い日々を送っております!
少しずつですが、庭の紅梅が、点ほどの赤いつぼみをつけ春の足音が、聞こえるようになってきました!
この時期の秋月にも是非、足をお運びください!
お待ちしております!
秋月のこれからの行事
3月17日(土曜日)18日(日曜日)19日(月曜日)20日(火曜日) 秋月 葛蔵開き
3月18日(日曜日) 第一回 秋月桜開き
4月1日(日曜日) 秋月桜祭り