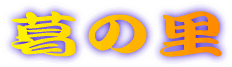|
 |
|
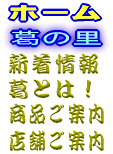
|
ごあいさつ 秋風のくずを訪ねて 田中恵子 八年ぶりに秋月にいって、その変わりように驚いてしまった。どこか時代ばなれして、おっとりとした山あいの静かな城下町だった秋月は、いつの間にか観光の町になってしまっている。 明治の初め、秋月の乱で、世間の目を集めたあと、時の流れを素通りさせてきたような町だった。それだけに。古いものがいっぱい残っていて、観光客の心をひきつけるのだろう。 町の入り口の眼鏡橋、秋月城の跡、黒門、長屋門といった文化財、土べいや石垣は昔のままだったが、郷土館の前には茶店がいくつも出来ていた。 空気が澄んでいておいしい。それに三種類くらい小鳥のさえずりが聞こえる。 同行の画家の小谷氏は『こんな空気のうまいところでは酒がうまいんですよ』と山菜をさかなに地酒を楽しんでおられた。 昔の秋月は・・・・などと思うのは感傷であろう。しかし文人墨客が遊びに来て、静かに時を過ごすといった情緒がまったくなくなってしまうのでは寂しい。 秋月は鎌倉時代、源頼家に秋月の荘を賜った原田種雄(たねかつ)が秋月姓を名乗って以来の城下町である。 秋月氏は、十六代種実が豊臣秀吉の九州征伐にあって宮崎高鍋に移封されるまでの約四百年間、古処山城を本城とし、杉本城を居城として支配した。 その後、関ヶ原の戦功あって筑前入りをした黒田長政の三子長興が秋月藩初代藩主となり、十二代長徳の版籍奉還まで約二百五十年が秋月黒田氏の城下町だった。 黒田氏の江戸時代には城下の産業育成にも力が入れられて、秋月特産の和紙とか、元結ロウ、それに本葛といったものが、藩の外貨獲得に活躍したようである。 しかし,明治、大正、昭和と時代が変わるとその特産もつぎつぎとすたれてしまって、今は秋月くずだけとなってしまっている。 なかで,手すきの秋月紙は、昭和三十年代まではまだすかれていたようだが、時代に流されて今はもうない。 アララギ派の歌人で紙塑人形の鹿児島寿蔵は、両親が秋月の出身で、少年の日秋月に遊ばれたこともしばしばだという。楮(こうぞ)を"カゴ"と呼んだ秋月和紙の技術を継承する人はいないのだろうか。このままなくなってしまうのは惜しいことだと思うのは私一人ではあるまい。 この冬は暖かいとはいっても秋月の冬は寒い。川沿いに甘木から登ってくると橋をひとつふたつと数えるごとに寒さが増してくる。 夏の秋月には、よくた潭空庵(だんごあん)に登ったりして涼をとりにきたものだが、一度だけ、冬の秋月に泊まったことがあった。 目を覚ますと障子の向こうが明るくて、寒さに首をちぢめながら障子を開けるといきなり白い世界が飛びこんできた。一夜にして出来上がった銀世界だった。あの『白』の印象は今も鮮やかに焼きついている。 秋月の町はどこを歩いても水の音がさやかに聞こえてくる。町家の庭に小川が引いてあったり、軒の端にも音をたてて清水が流れている。 手を入れると冬の水の冷たさをおもいしらされた。その冷たい冬の水でさらして、本くずは作りあげられる。 "かんねかずら"とよばれるくずの根は、昔は山野のいたるところに自生していた。このくずの根から良質のでんぷんをとり出し、純白にさらして作られたのが本くずである。昔から、原料が米の三倍が相場だという高価な物だからサツマイモのでんぷんで作ったにせものもよくある。 本くずの代名詞になっている『久助葛』を作っているのが秋月の廣田屋髙木久助氏のところである。 初代が文政の初め以来というから、ざっと百六十年の伝統を守ってきた廣田屋の今の当主は九代目である。 髙木家はバス通りにあって、古い造りそのままの二階建て。黒黒とした太いはり、入り口から仕事場へつづく黒土のひろい土間、二階へ上る階段は引出しや戸棚のついた箱階段と今ではなかなか見られない造りである。 表口の柱の大きな傷跡は、古い百姓一揆(き)の時のものだそうである。 九代目髙木久助氏は気さくな方で、誠実そうな目と働く人の手を持っておられる。 江戸時代の製法や店の創業のことを記した古文書や、金や銀で商売をしたころの『御用曝葛約帳』を見せていただく。町家ながら苗字帯刀御免の家柄だったことや、商いの数量が書かれていた。 『小さい時から手伝っていましたし、家業を継ぐのは当然のことと思ってきました。家伝の秘法といわれてもよそのことは全然知りませんし、親父のしてきた通りのことをやっているだけです。』伝統というのはそういうものなのであろう。 『やはり、戦時中の統制とインスタント食品におされたころが一番大変でした。今は自然食品が見直されたり、みやげものとしてもだいぶ出ています。』 昔は、秋月、江川、小石原といった山々で採れていたくず根も、山を切り開いてしまっていいものはとれないよし。行橋、熊本、鹿児島と遠方の山で採らせて運んでくる。 くずは寒い冬の間に掘る。そして、寒の時期の冷たい水にさらしたものを最上とする。 昔ながらの製法で、原料と水をかくはんする操作だけは動力を使うけれども、あとはみなカンと人手に頼る仕事である。二十年来の職人さんと久助氏の二人でさらし場の仕事が続く。 仕事場いっぱいに並んだおけの中で、何度も何度も冷水にさらされてまっ白のくずとなってゆく。型に流され、切って干されたくずの列は混じり気のない白、美しい"白"のかたまりだった。あの幼い日の純白の雪の思い出のように。 十年ほど前から、くずを知らない人のためにというので、『くず湯』『ごまどうふ』『梅くずもち』というパッケージが出されている。材料が全部入って、作り方がついて、簡単に"家庭でつくるふる里の味"が出せるようになっている。 本くずの味も、今の若い世代にはこうでもしないと受け入れられないのかも知れない。 夜更けに湯を沸かして、"作り方"通りに『くず湯』をつくってみる。かきまぜていると、昔のほのくらい台所や祖母のまがった背中がうかんでくる。病気になるといつも作ってもらったくず湯は、ほんのり甘く、とろりとふくらんで、おいしかった。 フウフウ吹きながら飲むと身体のしんから温まって、なつかしいくずの香りと味を思い出した。 |
|
「廣久本葛」「秋月本葛」「久助本葛」は廣久葛本舗の登録商標です |